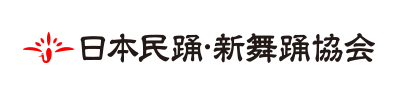2007年3月24日(土)開催
(東京四ツ谷・紀尾井小ホール)
300年以上前の日本で、八橋検校(1614〜1685)が創始した箏の弾き歌いによる歌曲、箏組歌。鳥居名美野師を代表とする現代邦楽研究所箏曲組歌研究会によって、近代箏曲の根本だった組歌の研究、研鑽が行なわれています。今回、山田流である鳥居師のみならず、他の流派の演奏家も多数集まって開催された、第6回箏曲組歌演奏会を取り上げます。また、箏組歌の奥義をさらに味わいたい方には、CD『鳥居名美野 箏組歌第一集』もあわせておすすめします。
*近代邦楽のエッセンス、日本のリート=箏組曲
文:星川京児
箏組歌は純邦楽のエッセンス

八橋検校が創始した箏組歌。王朝風の雅な歌詞に、これまたなんとも日本風なタメの効いた箏の伴奏が付いたもの。聴けば、一瞬にして花鳥風月、美しき日本の四季、風景、景物が浮かんでくるという、まさに純邦楽のエッセンスのようなジャンルである。それだけに、聴く方の感性、教養も計られてしまうという怖さもあるのだが。
それにしても八橋検校という人は凄い。彼の享年1685年は、あのバッハとヘンデルが生まれた年。昔、音楽の授業で習った、音楽の「父」と「母」が産声をあげた時、すでに箏曲、三味線、胡弓の近世邦楽の骨格は築かれていたのだ。
今回のプログラムは、山田流の鳥居名美野師を代表とする現代邦楽研究所箏曲組歌研究会主催だが、タイトルどおり、生田や継山など他流派も、伝承のスタイルをそのままステージに乗せて、それぞれの魅力を披露するという、ある種のガラ・コンサートとも言えるもの。こんな贅沢な時間は滅多に味わえるものではない。
総勢16人の奏者が舞台に乗る「天下太平」から「四季の友」「明石」「雲井曲」「心尽くし」「玉鬘」、鳥居名美野、山登松和の「若葉」まで全7曲。八橋検校3曲を入れて、表組、裏組、中組、奥組、そして平調子に雲井調子と、レパートリーも吟味・厳選されている。富山清琴、富山清仁組の齢による歌唱の対比など、歌唱のコントラストも面白い。
シューベルトにも優る日本歌曲
それにしても、邦楽というか、日本の伝統音楽・芸能においての歌(歌詞)の重要さは、ちょっと他に見当たらない。同じアジアの古典声楽をみても、ペルシアやインドには、人間離れした特殊な唱法があり、なかには詞を伴わないものすらあるのだ。中国の京劇や粤劇(※注)の唱法も、その特殊性は明らかだし、李朝の國樂の息遣いも、まずは唱法技術が優先する。それゆえに、門外漢でも判りやすいという部分もあるのだが。
ところが本朝の歌曲ときたら、歌詞が理解できて初めて曲の良さが見えてくるという、素人にはやっかいな代物。もちろん、詞の内容なんか判らなくても音楽的に十分楽しめるが、やはり風景、心情が伝わるには、ある程度の理解は必要。今回だけでなく、大概のプログラムに詞が掲載されているのも、このことと無関係ではないだろう。本来は、聴衆も含めて、誰もが歌詞を共有していたのだろう。江戸ブルジョア文化の極致。江戸のサロン・ミュージックと言い換えてもいい。
このことは日本人の洋楽受け入れ過程と似たところもある。最初に交響曲などオーケストラもので入っても、そのうち室内楽の良さが見え始め、最後は歌曲。オペラや古楽、バレエに行くのは嗜好の問題としても、リートとなったらけっこう難しい。それだけに嵌ったら抜けられない魅力があるのか、熱狂的なファンが多い。リートも、ゲーテなど詩人の作品に、きっちりと対応する譜面上の決まり事があり、ドイツ的詩情というものと切り離せない。そう考えれば、八橋検校は日本歌曲の先駆けでもあったのか。
あのシューベルトにも優っていたということですね。
※写真はリハーサル時のもの
※注:粤劇(えつげき、ユッケッ)
中国の広東地方で受け継がれている歌舞劇。北京の京劇同様、チャイニーズオペラとして知られている。
星川京児(ほしかわ きょうじ)
1953年4月18日香川県生まれ。学生時代より様々な音楽活動を始める。そのうちに演奏したり作曲するより製作する方に興味を覚え、いつのまにかプロデューサー。民族音楽の専門誌を作ったりNHKの「世界の民族音楽」でDJを担当したりしながら、やがて民族音楽と純邦楽に中心を置いたCD、コンサート、番組製作が仕事に。モットーは「誰も聴いたことのない音を探して」。プロデュース作品『東京の夏音楽祭20周年記念DVD』をはじめ、関わってきたCD、映画、書籍、番組、イベントは多数。















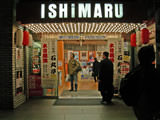





















 昭和8年、奄美大島郡瀬戸内町生まれ。小学校の頃からしまうたが好きで父や従兄弟叔父にあたる福島幸義氏に詩吟やしまうたを師事し、青年時代は古仁屋に出て働きながら奄美民謡を研究。昭和36年、文部省主催の芸術祭に出演以降数多くの公演、テレビ出演、レコード、CD、ビデオが発売されて一躍有名となり「奄美民謡武下流」を打ち立てる。平成8年にはしまうたを芸術まで高めたことが認められ「尼崎市民芸術賞」を受賞。沢山の門下生を養成し、奄美民謡界「百年に一人の唄者」と称され、多くのしまうたファンを魅了し続けている。
昭和8年、奄美大島郡瀬戸内町生まれ。小学校の頃からしまうたが好きで父や従兄弟叔父にあたる福島幸義氏に詩吟やしまうたを師事し、青年時代は古仁屋に出て働きながら奄美民謡を研究。昭和36年、文部省主催の芸術祭に出演以降数多くの公演、テレビ出演、レコード、CD、ビデオが発売されて一躍有名となり「奄美民謡武下流」を打ち立てる。平成8年にはしまうたを芸術まで高めたことが認められ「尼崎市民芸術賞」を受賞。沢山の門下生を養成し、奄美民謡界「百年に一人の唄者」と称され、多くのしまうたファンを魅了し続けている。 昭和31年奄美大島瀬戸内町古仁屋に父・武下和平の長女として生まれる。昭和61年兵庫県神戸市に両親とともに転居。平成14年奄美民謡武下流門下生として正式入門。平成16年父・和平の相方として特別出演。以降、父和平の相方として各イベントに参加しながら研鑽中。
昭和31年奄美大島瀬戸内町古仁屋に父・武下和平の長女として生まれる。昭和61年兵庫県神戸市に両親とともに転居。平成14年奄美民謡武下流門下生として正式入門。平成16年父・和平の相方として特別出演。以降、父和平の相方として各イベントに参加しながら研鑽中。