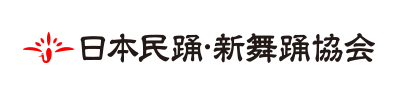zen yamato
2011年10月24日(月)開催
(東京・津田ホール)
今年で結成5年を迎えた尺八・善養寺惠介師、山田流箏曲・山登松和師の古典にこだわるユニット、Zen Yamato。東京・津田ホールでの公演は、箏の名手・亀山香能師、尺八の徳丸十盟師という豪華な賛助出演を迎えて開催されました。多数の聴衆が詰めかけ、終演後は惜しみない拍手に包まれた公演の模様を邦楽評論家の笹井邦平さんのレポートでお送りします。
文:笹井邦平
最高のデュオ
会名のzenとは尺八演奏家・善養寺惠介師、yamatoとは山田流箏曲演奏家・山登松和師で、つまりこの2人のジョイントコンサートである。
2人は東京藝術大学の1年違いの先輩後輩、善養寺師は昨今の箏曲リサイタルには殆ど出演している売れっ子。山登師は山田流箏曲で山勢派・山木派とともに〈御三家〉と云われる名門山登派の七代家元、やはり昨今の演奏会では助演でよく舞台に立っていた。つまりこの2人は実力・人気を兼ね備えた今が旬の最高のデュオなのである。
江戸時代のポピュラーソング

序曲は八橋検校作曲・中組「雲井弄斎(くもいろうさい)」(箏-山登松和、尺八-善養寺惠介)。箏曲演奏家の必須テキストである〈箏組歌〉に付随する組歌で、曲名の〈雲井〉とは箏の調弦法の〈雲井調子〉のこと、〈弄斎〉とは江戸時代に流行った小歌謡の一種で、「ノウ」や「サユエ」などと囃子言葉が入り、純然たる〈箏組歌〉よりやや砕けたテイスト。といっても〈組歌〉と尺八を合わせるのは大御所が顔をしかめるかもしれぬが、このユニットは結成以来〈箏組歌〉と尺八のジョイントにチャレンジしているので違和感はない。
山登師のかっちりした爪音と善養寺師の深みのある尺八の音色がそれを証明し、山登師の哀調を帯びた サユエ」という囃子言葉に庶民の生活の匂いが漂う。
ハイテンションのアンサンブル

2曲目は吉沢検校作曲「千鳥曲」(箏-山登松和、尺八-徳丸十盟・善養寺惠介)。作曲者が『古今和歌集』の和歌を採り入れて四季を綴った「春の曲」「夏の曲」「秋の曲」「冬の曲」にこの「千鳥曲」を加えた5曲を〈古今組〉といい、「千鳥曲」のみ後歌は『金葉和歌集』から採っている。
今回は善養寺師のアイディアで尺八古典本曲「鹿の遠音」のように尺八2管でメロディラインを吹き分けて箏と合奏する-という斬新なスタイル。その白羽の矢が立ったのが善養寺師の先輩で藝大時代ともに山口五郎師に師事した徳丸十盟師。着かず離れずの微妙な流れを構築する2管の尺八に挟まれた山登師は凛とした歌とクリアな爪音でこの二人に対峙し、そのハイテンションのアンサンブルが波音や千鳥の鳴き声といった長閑な海辺の景色を鮮やかに映し出す。

3曲目は松本一翁作詞・三つ橋勾当作曲「根曳の松」(箏-亀山香能、三絃-山登松和、尺八-善養寺惠介)。掉尾は最高格の祝儀物で飾る。最高というのは音楽的完成度はむろんだが難易度も最高で演奏家なら一度弾いてみたい憧れの曲。平安時代正月初子(はつね)の日に野に出て小松を引き抜いて長寿を祝う〈子の日の遊び〉に因む初春の情景を綴った曲、聴かせ処は三つある手事で箏・三絃・尺八ともに最高の技術が要求される。そのパートナーに山登師はこの曲のスペシャリスト亀山師を選んだ。この二人の火花を散らすバトルに善養寺師は前2曲とは異なる1歩引いたスタンスで撥弦楽器の間を縫いハイレベルな三曲合奏を聴かせる。
バイタリティ溢れるユニット
3曲ともに古典に対する敬意の念とチャレンジ精神が同居し、21世紀を生き抜く古典としての価値観を見出そうとする意気込みが漲る。その想いを最高の技術と逞しい創造力で叶えようとする-zen yamatoとはそんなバイタリティ溢れるユニットである。
写真:オガワブンゴ(リハーサル時の撮影)
■プロフィール
善養寺惠介
1964年生まれ。6歳より父昭三と岡崎自修師(いずれも神如道門人)に虚無僧尺八の手ほどきを受ける。
| 1982年 | 神如正師に師事。 |
| 1990年 | 東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。 |
| 学部、大学院を通じて人間国宝、山口五郎師に師事。 | |
| 1998年 | 国際尺八フェスティバル(コロラド州ボルダー)に招待演奏家として参加。 |
| 1999年 | 第1回独演会『虚無尺八』開催、今までに9回を重ねる。 |
| 2000年 | 尺八教則本「はじめての尺八」(音楽之友社刊)を執筆。 |
| 2002年 | 第6回ビクター財団賞「奨励賞」受賞。世界銀行主催、世界宗教者国際会議(於イギリス カンタベリー大聖堂)にて招待演奏。 |
| 2008年 | 第8回リサイタル『善養寺惠介尺八演奏会』(トッパンホール)にて文化庁芸術祭賞新人賞を受賞。 |
| 2009年 | 第9回リサイタル『虚無尺八』(トッパンホール)にて文化庁芸術祭優秀賞を受賞。 |
そのほか、国際交流基金派遣などによるヨーロッパ、アジア各地での公演多数。東京藝術大学非常勤講師を務めた後、現在は関東各地(東京、埼玉、群馬)の尺八教授活動も行っている。百錢会主宰、有明教育芸術短期大学、NHK文化センター町田・川越・高崎・横浜講師。
山登松和
1966年生まれ。4歳より山田流箏曲山登派五代家元山登愛子(祖母)に箏の手ほどきを受ける。以後、中能島欣一師に箏、鳥居名美野師に箏・三弦を師事する。
| 1989年 | 東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。安宅賞受賞。 |
| 河東節三味線を山彦さわ子師に師事。 荻江節三味線を荻江さわ師に師事。 |
|
| 1991年 | 東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。 |
| 1994年 | 国際交流基金派遣専門家として、アフリカ(4ヵ国)公演に参加。 |
| 1995年 | 東京藝術大学非常勤講師を務める(96、01、02年)。 |
| 河東節浄瑠璃を山彦節子師に師事。 山彦登の名を許される。 |
|
| 1999年 | 山登派七代家元山登松和を襲名。 |
| 国立劇場小劇場にて襲名披露演奏会。 | |
| 2001年 | 第5回ビクター財団賞「奨励賞」受賞。 |
| 2002年 | 第1回山登松和の会(紀尾井小ホール)にて文化庁芸術祭優秀賞受賞。 |
| 2003年 | 荻江さわ師より荻江登の名を許される。 |
| 2006年 | 第2回山登松和の会(国立劇場小劇場) |
| 2008年 | 第29回松尾芸能賞新人賞受賞。 |
| 2009年 | 第3回山登松和の会(紀尾井小ホール) |
山登会主宰、公益社団法人日本三曲協会理事、山田流箏曲協会理事、跡見学園中学・高等学校箏曲講師。
亀山香能(かめやま・こうの)
6歳より海老名久駕師、12歳より野口美喜緒師に師事。
| 1960年 | 東京新聞主催、文部省・日本放送協会後援「邦楽コンクール」にて三曲児童部2位入賞。 |
| 1969年 | 東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。在学中、箏・三弦を人間国宝・中能島欣一師に師事。 |
| 皇居内桃華楽堂にて御前演奏。NHKラジオ初出演。以降NHKラジオ「邦楽のひととき」「邦楽百番」、NHKテレビ「日本の調べ」「芸能花舞台」をはじめNHK・BSにも度々出演、現在に至る。 | |
| 1972年 | 東京藝術大学大学院修士課程修了。この年より78年まで東京藝術大学に助手として勤務。以降非常勤講師を務める。 |
| 1973年 | 中能島欣一師より名号(香能)教授許さる。 |
| 1976年 | NHK依頼により、首相(福田赳夫)官邸にて演奏。 |
| 1979年 | 第1回リサイタルを開催(以降2009年までに15回のリサイタルを開催)。 イギリス・Duraban大学東洋音楽研究所主催「東洋音楽祭」に鳥居名美野師と参加演奏。 |
| 1983年 | NHKテレビ「箏のお稽古」で人間国宝・六代山勢松韻師のアシスタントを一年にわたり務める。 |
| 1985年 | 河東節三味線を山彦さわ子師に師事。 |
| 1993年 | 仙台にて「中能島欣一作品の夕べ」リサイタル開催。 |
| 1998年 | 国際交流基金よりドイツ、イタリア、ベルギーにて演奏(国際交流会)。 |
| 2000年 | オーストラリアのメルボルン、キャンベラ、シドニー三都市にて演奏(国際交流会)。 |
| 2002年 | この年より年3回のペースで「亀山香能Talk&Live」を開催し現在に至る(〜15回)。 |
| 2004年 | 津田ホールにて開催された「BIWAKOTOFUE」に、福原徹氏、中川鶴女氏と共に出演する。「中能島欣一生誕100年記念」のタイトルにて、つくば 市、甲府市、仙台市、千葉市、盛岡市でライブ公演を行う。この年より年3回のペースで、地方ライブ公演を開催し、現在に至る。 |
| 2005年 | 第13回リサイタルにて文化庁芸術祭優秀賞受賞。CD「時を紡いで」リリース(1〜3集)。 |
| 2009年 | 邦楽TT支援ボランティア企画(白石市能楽堂)「箏の調べ」―能と山田流箏曲―に出演。“SOUND of 和楽”(年2回の6回シリーズ)を開始。 |
現在、国内外の演奏及びテレビ、ラジオ、歌舞伎座などに出演活躍。学校コンクールの審査員をつとめ、後進の指導及び日本音楽普及のためのワークショップ、レクチャーコンサートなどにも力を注ぐ。
桐香会主宰、奏心会代表、日本音楽国際交流会幹事、洗足学園音楽大学現代邦楽研究所講師、(財)音楽文化創造委員。明治薬科大学、日本豊山女子中学・高校、白百合学園中学・高校の箏曲講師。
箏組歌会、BIWAKOTOFUE、新潮会、北区三曲三和会、三曲若葉会、中能島会、山田流箏曲協会、日本三曲協会所属。
徳丸十盟(とくまる・じゅうめい)
東京都出身。幼少より父に琴古流尺八の手ほどきを受ける。
| 1984年 | 東京芸術大学音楽学部邦楽科尺八専攻卒業。 |
| 1987年 | 同大学院修士課程修了。 在学中より山口五郎師に師事、卒業後直門となり師範の許しを得る。 |
| 1986年 | NHK邦楽オーディション合格。 |
| 1993年 | トルコ・ハンガリーを巡演。同年、師・山口五郎と共にインド国内を巡演。 |
| 1994年 | アフリカ各国(タンザニア・ガーナ・南アフリカ・スーダン)を巡演。 |
| 1996年 | アメリカ国内を巡演。 |
| 1998年 | 世界尺八フェスティバル(米国コロラド州ボルダー)招待演奏。ロシア・カザフスタンを巡演。ドイツ・イタリア・ベルギーを巡演。 |
| 2000年 | 第1回ビクター邦楽技能者オーディションに合格。 |
| 2003年 | ウズベキスタンで演奏。 |
| 2004年 | イタリア・パドヴァ市にて本曲リサイタルを開催。 |
| 2005年 | フランス・パリのユネスコ本部で60周年記念コンサートにて演奏。 |
| 2006年 | イギリス・ロンドンにて演奏。 |
| 2007年 | ロシア国内を巡演。 |
| 2008年 | 世界尺八フェスティバル(オーストラリア・シドニー)招待演奏。 |
| 2011年 | 徳丸十盟インド尺八巡礼。同年、ドイツ国内演奏旅行。 |
2007年(第1回)、08年(第2回)、10年(第3回)徳丸十盟尺八演奏会開催。
1989〜2005年 数期に渡り、東京藝術大学非常勤講師を務める。
平成19年度(第58回)芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。平成20年度江戸川区文化奨励賞受賞。
琴古流尺八雅道会主宰、日本三曲協会参与、琴古流協会評議員、読売文化センター・産経学園講師。
笹井邦平(ささい くにへい)
1949年青森生まれ、1972年早稲田大学第一文学部演劇専攻卒業。1975年劇団前進座付属俳優養成所に入所。歌舞伎俳優・市川猿之助に入門、歌舞伎座「市川猿之助奮闘公演」にて初舞台。1990年歌舞伎俳優を廃業後、歌舞伎台本作家集団『作者部屋』に参加、雑誌『邦楽の友』の編集長就任。退社後、邦楽評論活動に入り、同時に台本作家ぐるーぷ『作者邑』を創立。
(記事公開日:2011年11月17日)